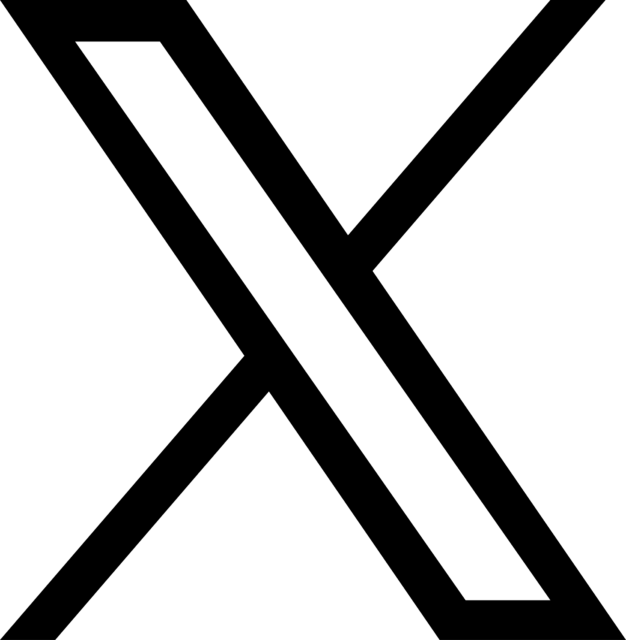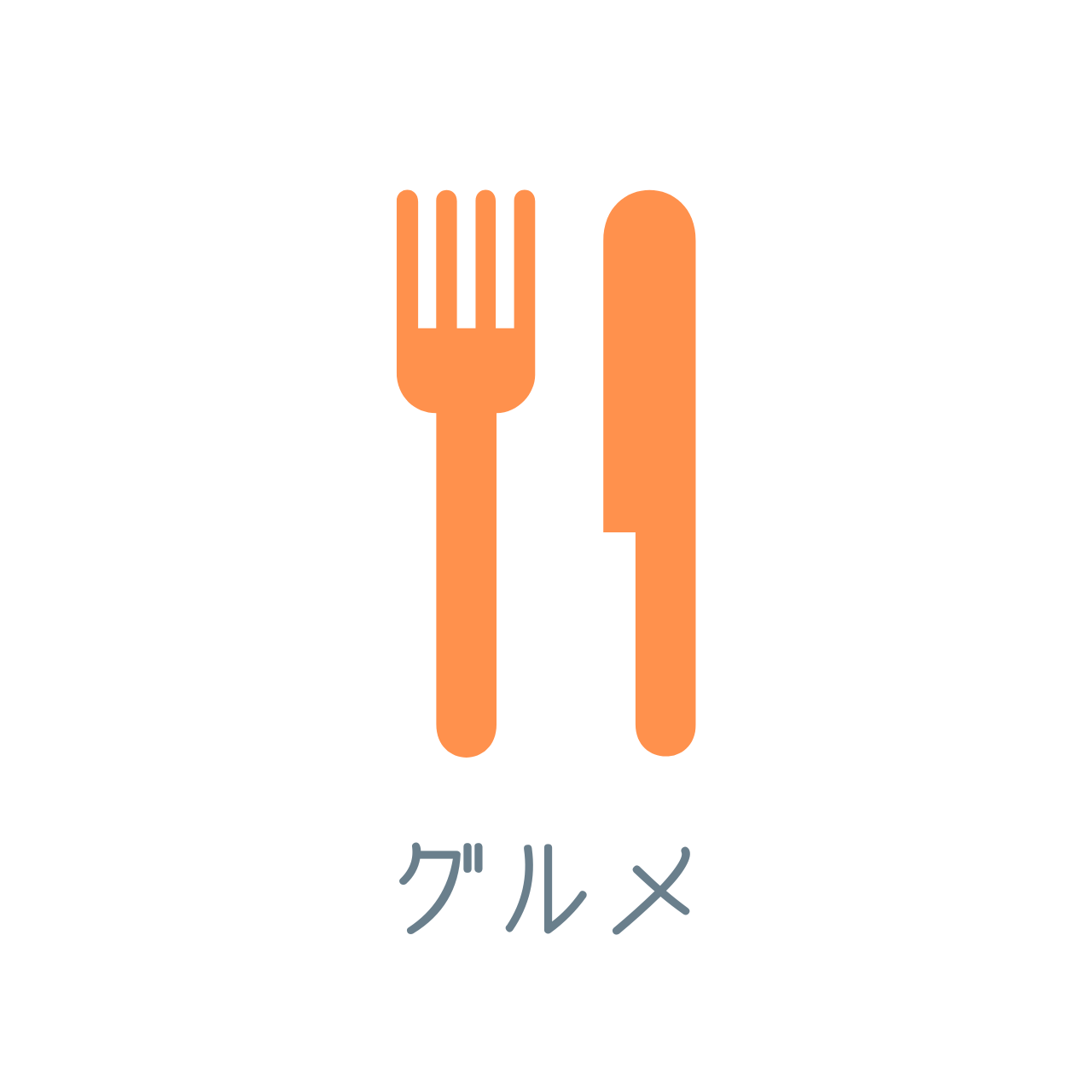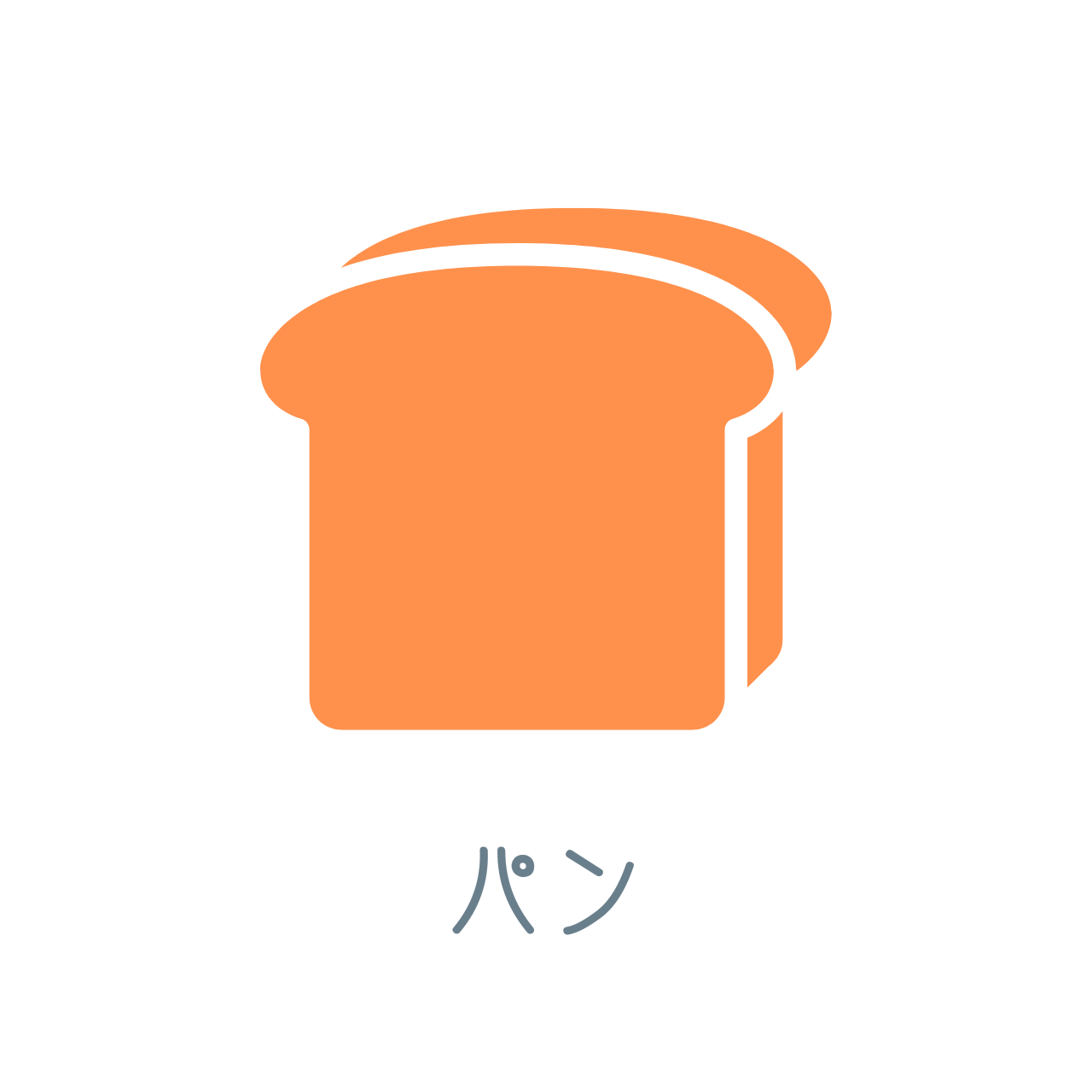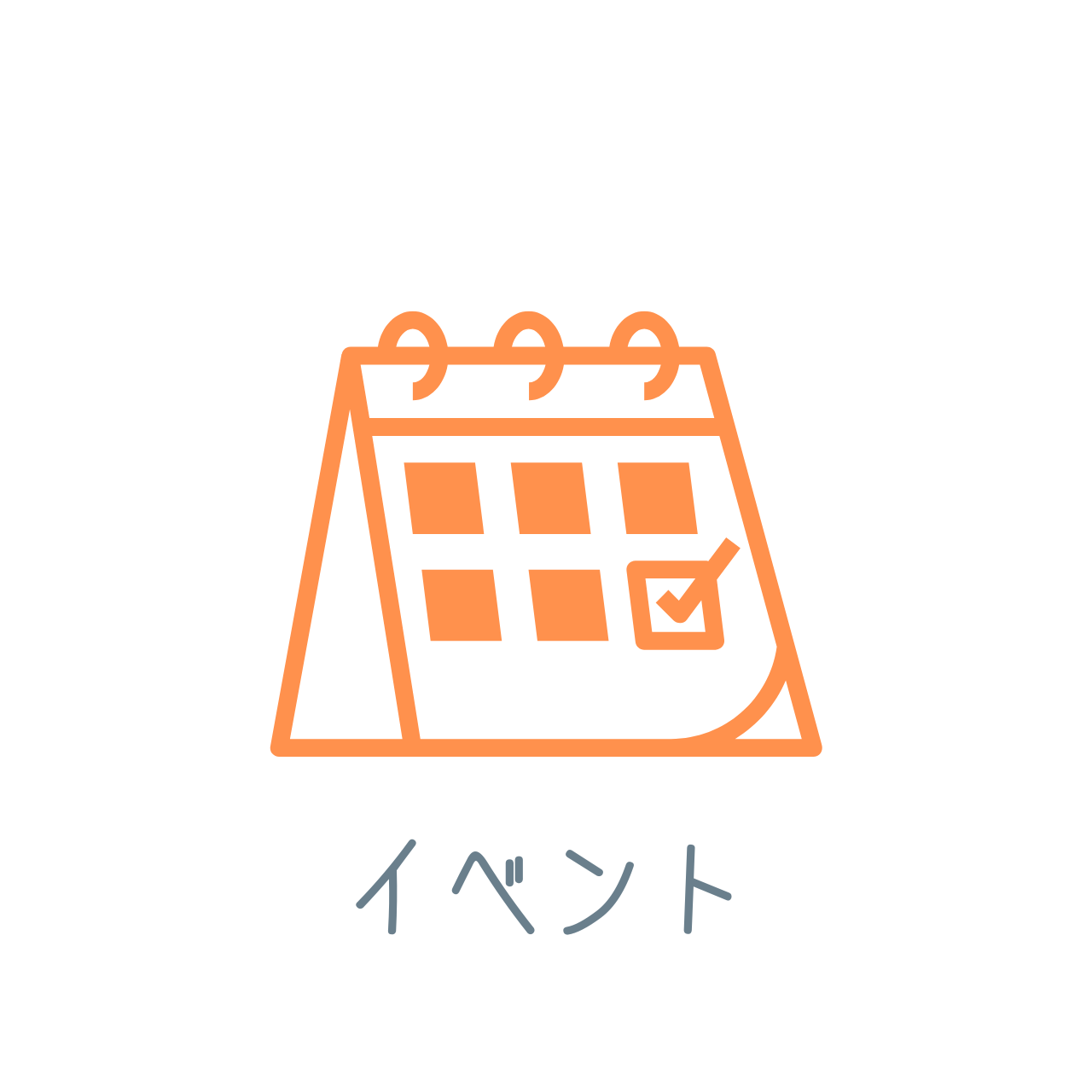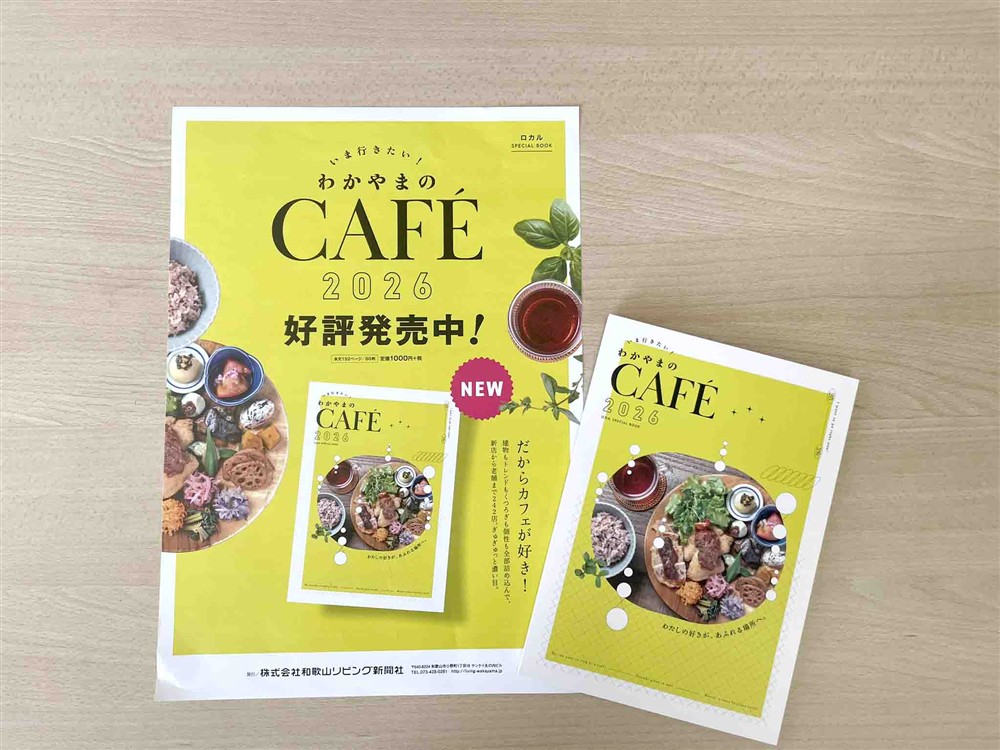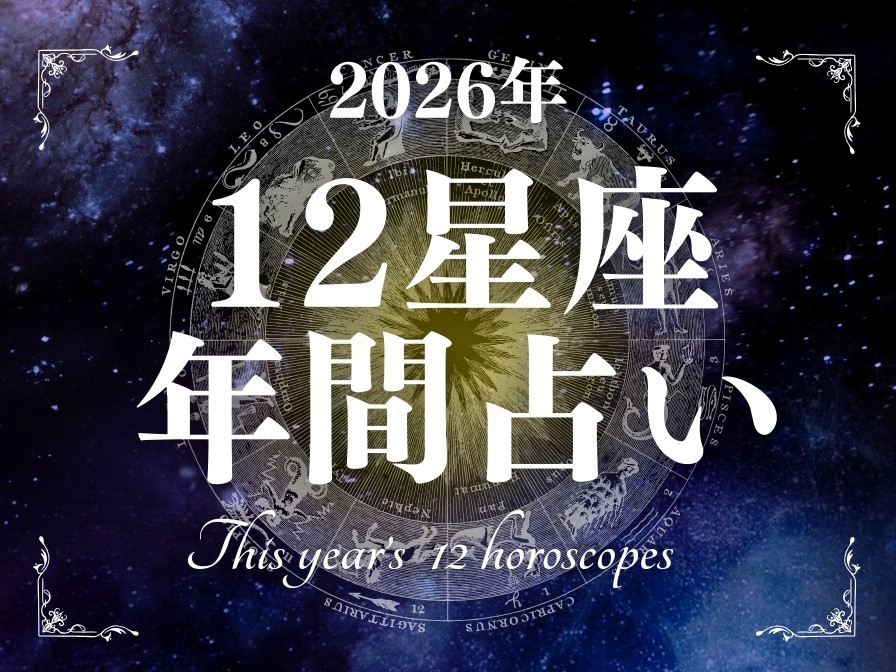200年ぶりの大修理 和歌浦天満宮で計画進む
イチオシの記事
日本三菅廟の一つとして長く信仰を集めている和歌山市和歌浦西の和歌浦天満宮で、1835年に徳川治宝(はるとみ)が大改修工事を行って以来、200年ぶりとなる「令和の大修理」工事の計画が進められている。
【写真】西回廊を祓い清める小板宮司
和歌浦天満宮は、平安時代の康保年間(964~68)に菅原道真を祭る神殿が建立されたのが始まりとされる。天正13年(1585)の羽柴秀吉の紀州攻めの際に社殿は焼失したが、慶長11年(1606)に徳川家入国前の紀州藩主・浅野幸長が現在の社殿を再建。同宮は歴史的な景観として国の名勝「和歌の浦」に指定され、本殿と楼門、奥にある桃山時代建立の末社2棟が国の重要文化財になっている。
県文化財センター文化財建造物課の多井忠嗣課長は治宝の改修工事について「紀州徳川家は大がかりな修理を行うごとに修理棟札(むなふだ)という木の板に書かれた記録を残している。徳川治宝が改修した棟札は2枚あり、1枚には本殿の塗装工事を京都の職人が担当したことなども記載されており、当時の修理の規模の大きさがうかがえる」と話す。
それから190年の月日が経ち、長年の風雨に耐えてきた建物は老朽化が進んでいる。特に石垣の上に建つ東西の回廊は柱が傾くなどの劣化が見られている。
西回廊は書き初め大会や茶会などの催しで多くの人が使用することから、安全のための改修が急務とし、まずは来年1月までに仮の耐震耐風工事を行う。その後、治宝が大改修工事をした200年後となる2035年に大掛かりな修理を行う計画。
工事費用の半分は国や県の補助を受け、残りは地元からの寄付や募金を検討している。
2035年ごろには本殿の檜皮葺の葺き替えが必要となってくるため、傷みが目立つ透き塀なども併せて、地元からの寄付などが集まり次第、各建物の修理を進めていくという。
6日には令和の大修理奉告祭が執り行われ、関係者らが改修計画を神前に報国。1月から境内に看板などを設置し募金を呼びかける予定。
桃山・江戸時代には時の為政者が、明治になってからは「和歌浦の氏神さん」として、地元の人たちが保護し守ってきた和歌浦天満宮。小板政規宮司は「歴史の中では幕府の藩主がそれぞれ改修工事をしてきたが、今回はみんなの力で次世代につなげたい」と話している。