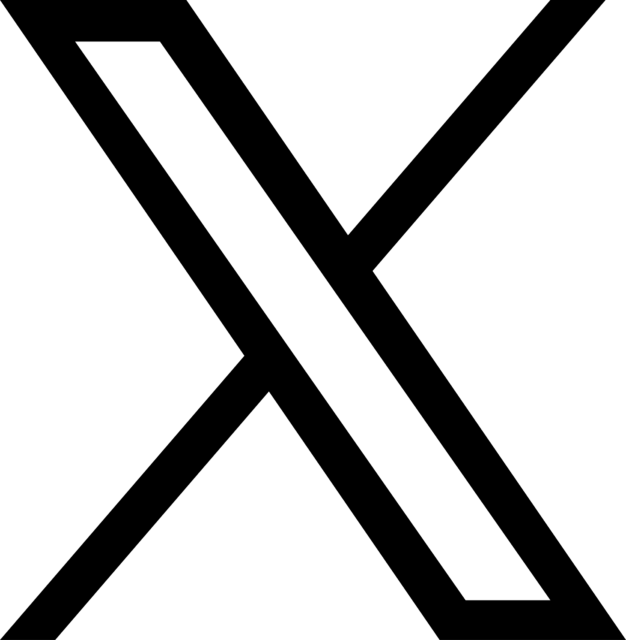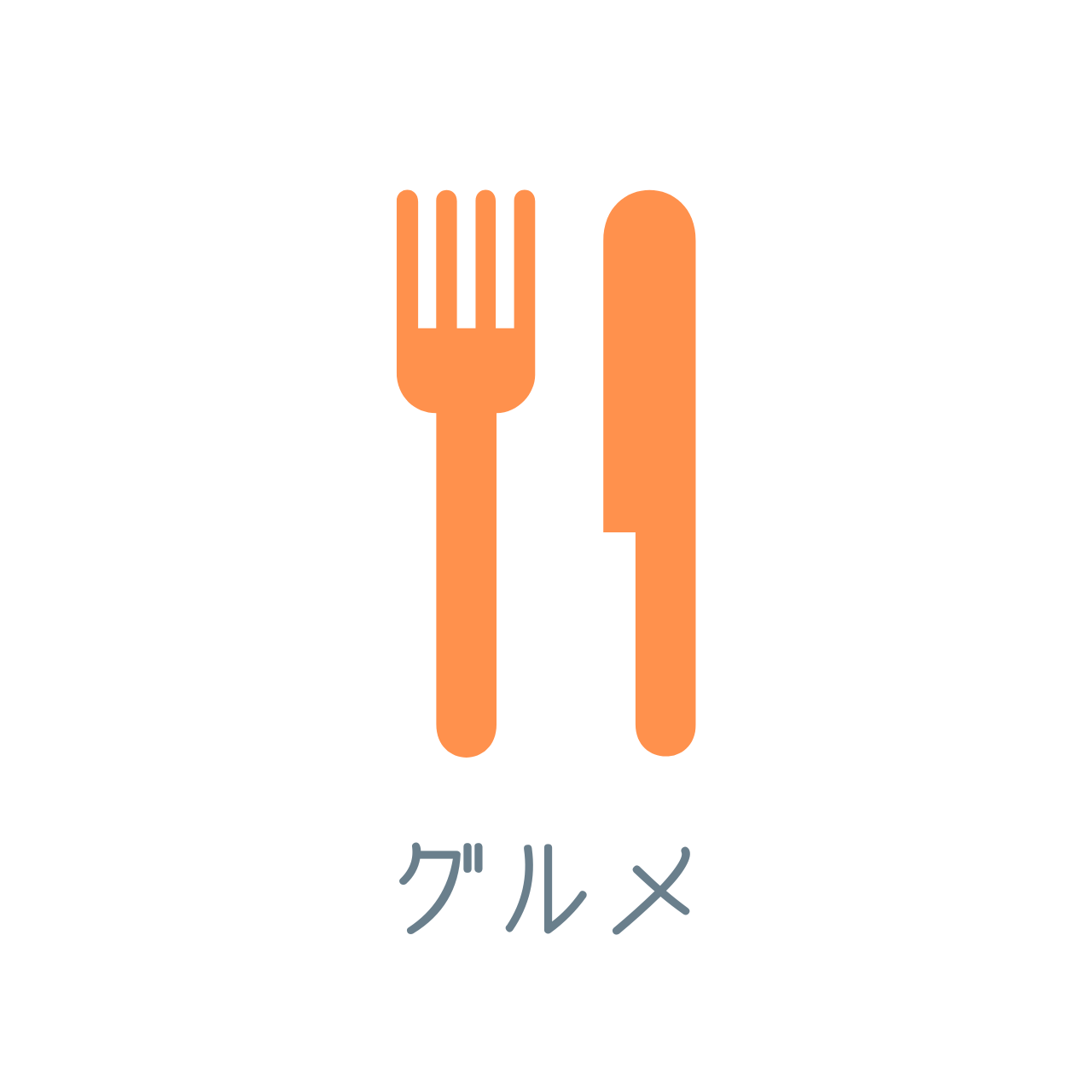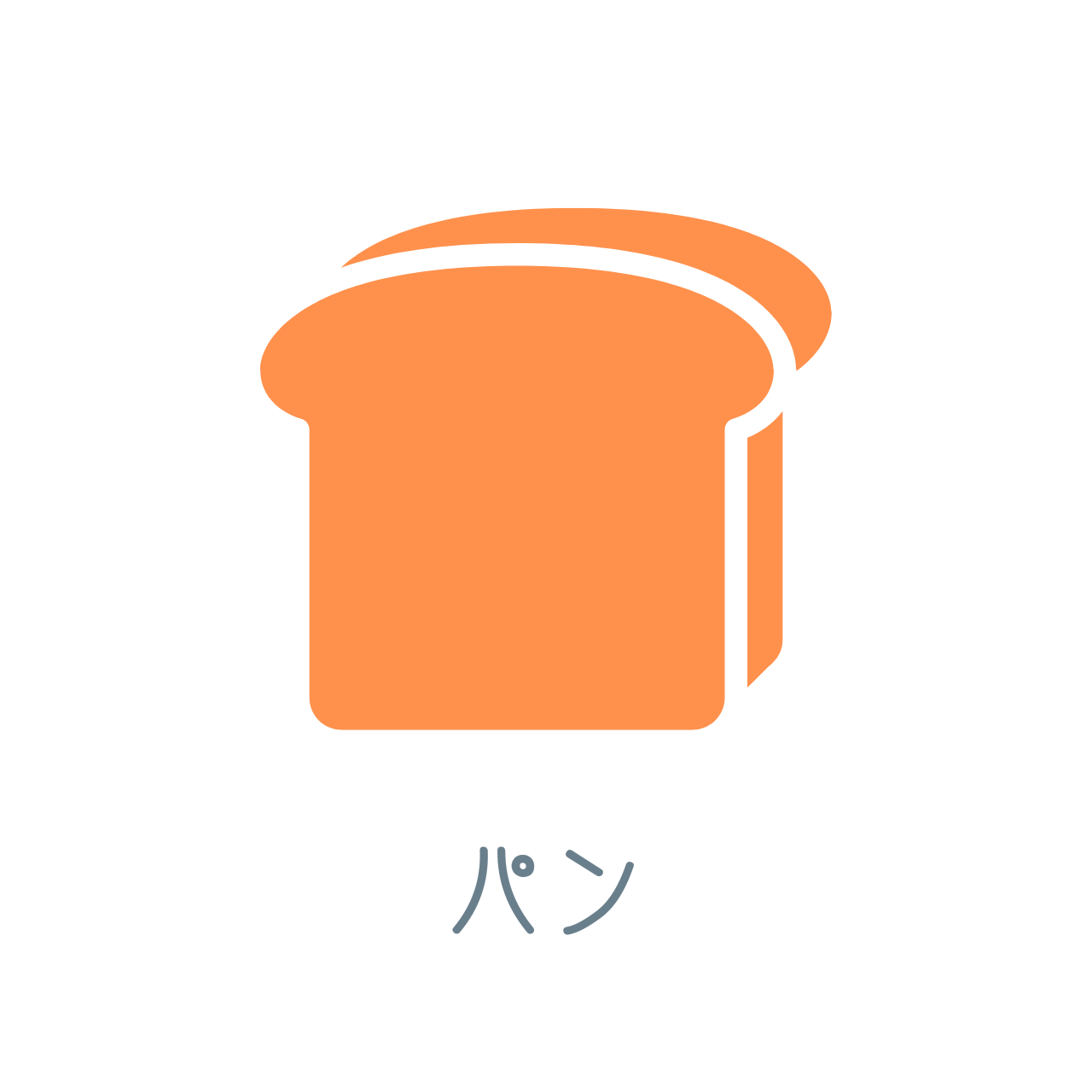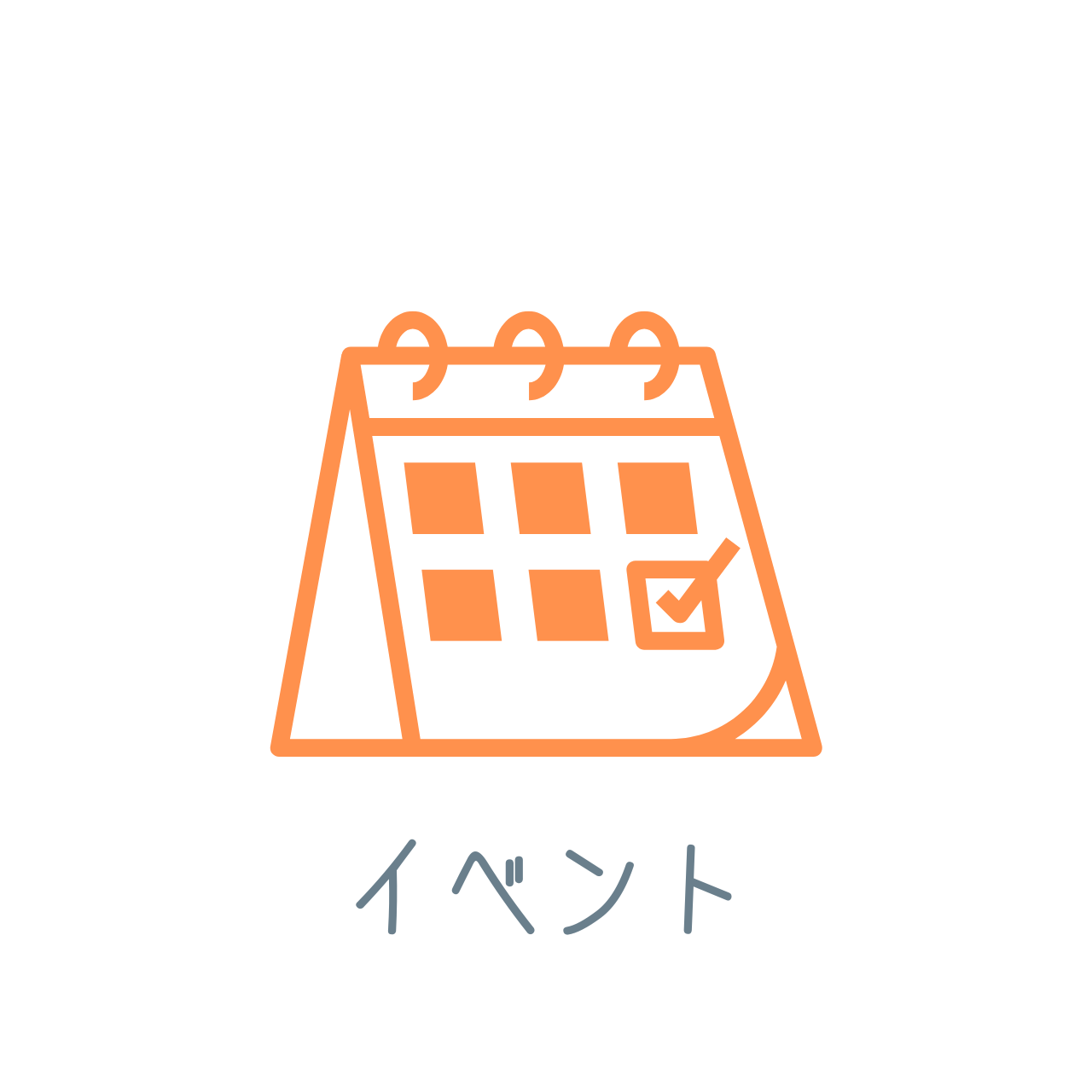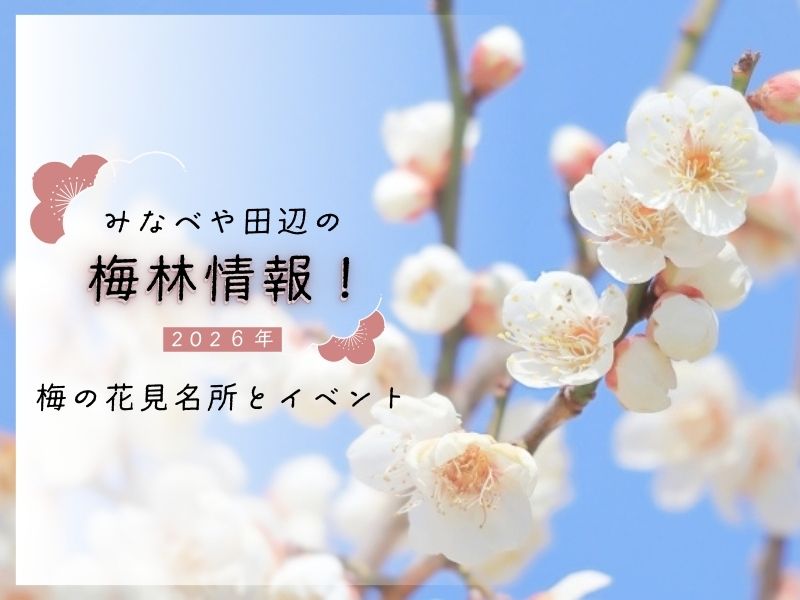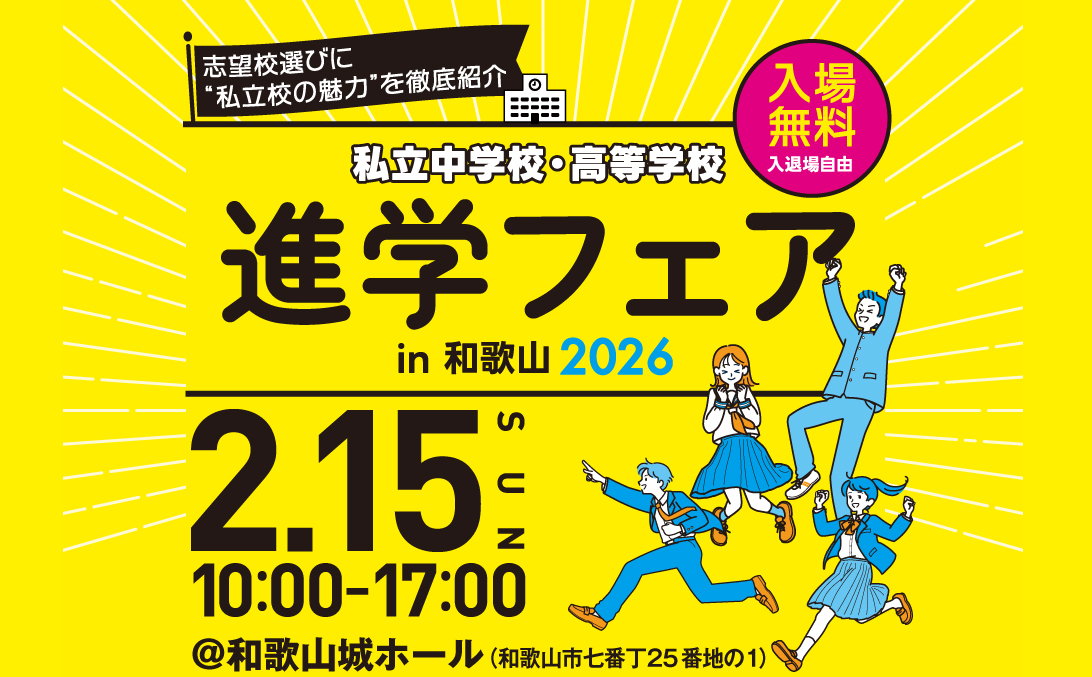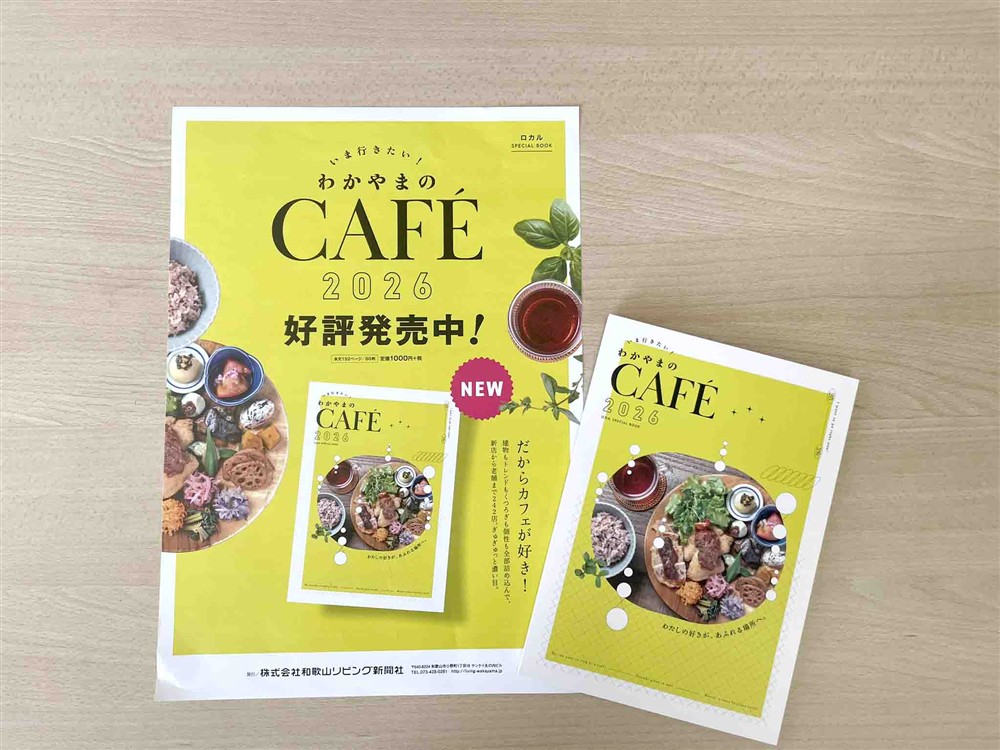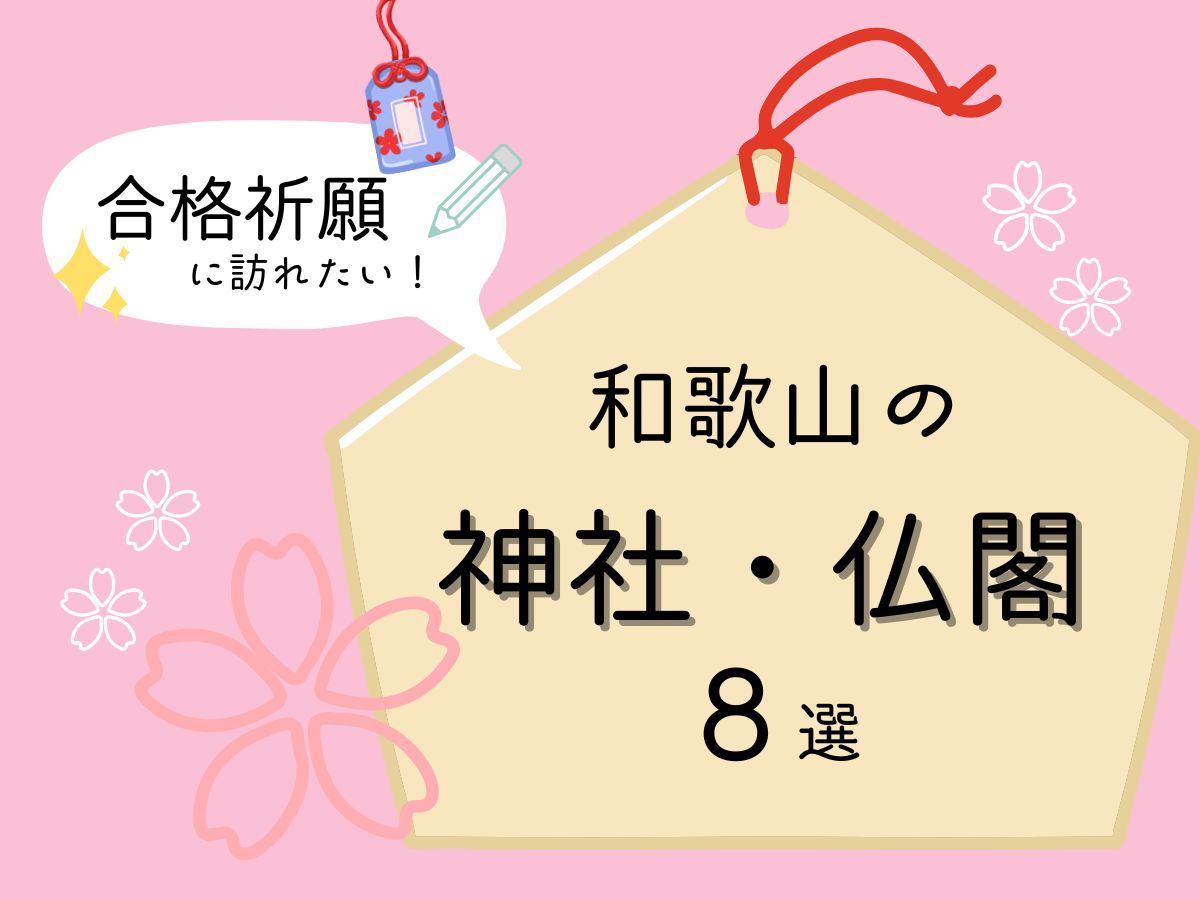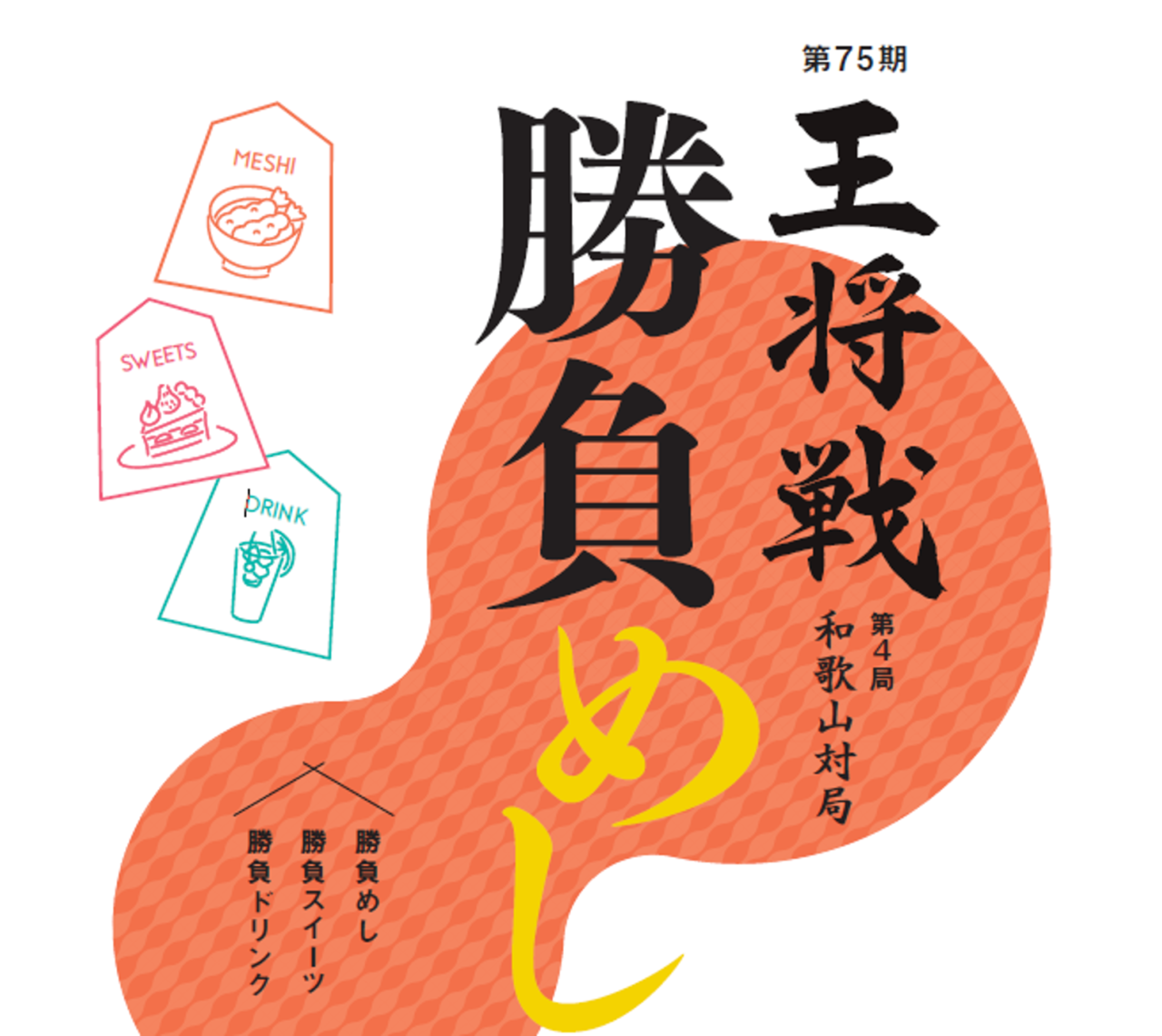『和歌山今昔物語』第3集 紀州文化の会が発刊
イチオシの記事
文化の力で和歌山を活性化しようと活動する「紀州文化の会」(大江寛代表)が毎年出版している「あがらの和歌山」シリーズの第18弾『気になる和歌山今昔物語』第3集が19日、発売される。和歌山市各地区の成り立ちや移り変わり、代表的な店舗などを紹介するシリーズの3冊目。今回は市西部の国道24号、大浦街道が通るエリアを対象に、政治の中心の県庁周辺、景勝地「和歌の浦」などを取り上げている。
【写真】『気になる和歌山今昔物語』第3集を手に、紀州文化の会の皆さん
同会は2004年7月に発足し、6人の会員が活動。「ええとこあるで和歌山」を合言葉に、和歌山のファンを増やそうと、地元の歴史、地名、方言、人物など幅広いテーマを扱う出版活動を続け、制作した書籍は今回で20冊目となる。
進行中のシリーズ『気になる和歌山今昔物語』は、「一般の歴史書には載っていない、街の裏まで掘り下げた内容を」と企画。本町・城北地区を紹介した第1集を2023年7月、JR和歌山駅西側の商業地や歓楽街を含む6地区を紹介した第2集を24年4月に発刊し、全6巻を予定している。
第3集の対象は、雄湊、吹上、砂山、高松、雑賀、和歌浦、雑賀崎の7地区。地名の由来や歴史は、現在は住所表記からなくなったものも含めて紹介し、各地域の代表的な企業や店舗、娯楽施設、商業施設などの紹介は今回も充実しており、創業や移転、廃業などの変遷の歴史を詳しく収録した。
県庁がある小松原一丁目の紹介では、政治の中心地にちなみ、昭和初期から戦後にかけての物価、公務員の初任給、高額所得者の確定申告額など、当時の市民生活をうかがい知ることができるデータも掲載している。
和歌浦地区については、日本遺産の構成資産として現在も残る神社や文化財の紹介をはじめ、夏目漱石も明治44年に訪れた奠供山の屋外展望エレベーターなど、今は失われた文物の歴史も知ることができる。
表紙と裏表紙は、明治時代に竣工した初代、二代目の県庁舎の写真を使用。巻頭の古写真コーナーには、現在の県庁舎の建設中の様子、黒潮国体に出席した昭和天皇皇后の車列、和歌浦を撮り続けてきた写真家・松原時夫さんが提供した海苔養殖の光景など、往年の和歌山を記録したモノクロ写真が並んでいる。
前書きは和歌山大学の本山貢学長が執筆。今回も、対象地区に在住やゆかりのある各界の13人が、思い出の場所や人物などについてコラムを寄せている。
大江代表は「年配の皆さんには懐かしい思い出として楽しんでもらい、若い人たちには、和歌山はこんなに元気だったということを知ってもらい、自分も頑張ろう、和歌山を盛り上げていこうと思ってもらえたらうれしい」と話している。
B5判、448㌻。定価2480円。県内の主要書店などで取り扱う。問い合わせは紀州文化の会(℡090・1222・6495)。