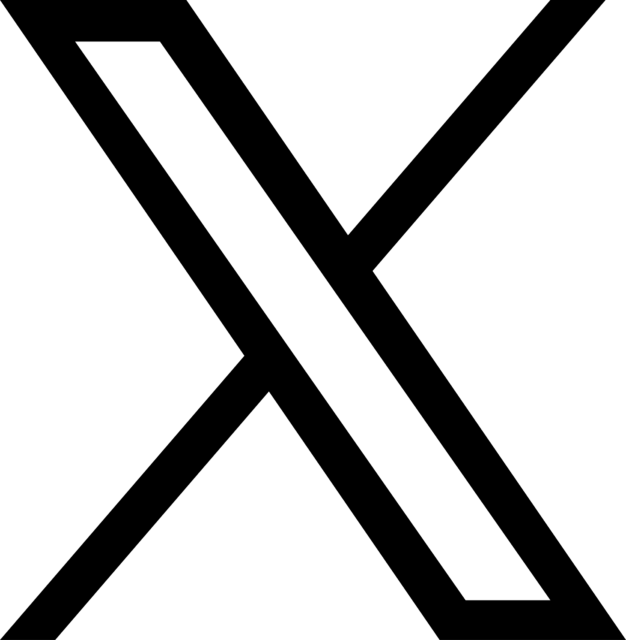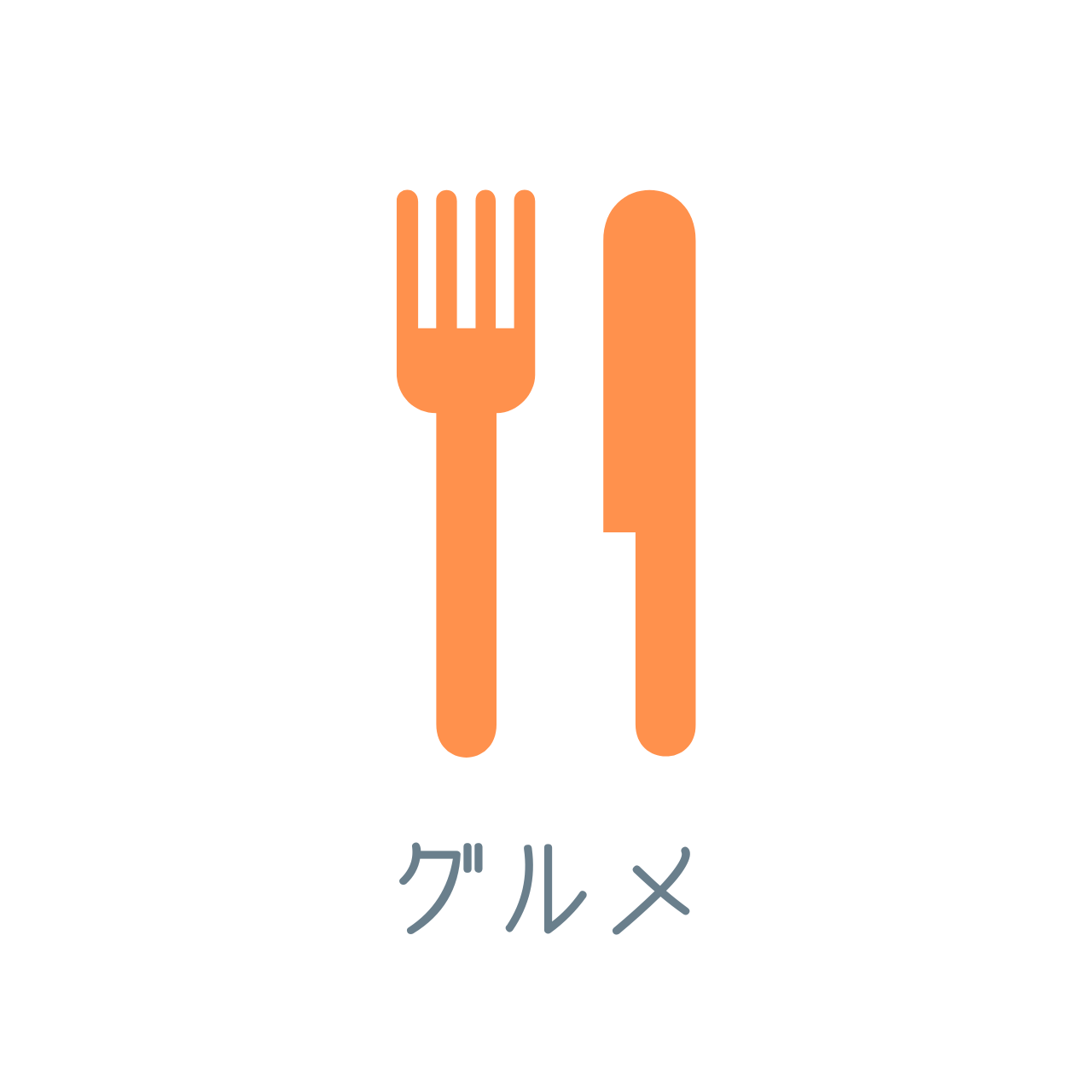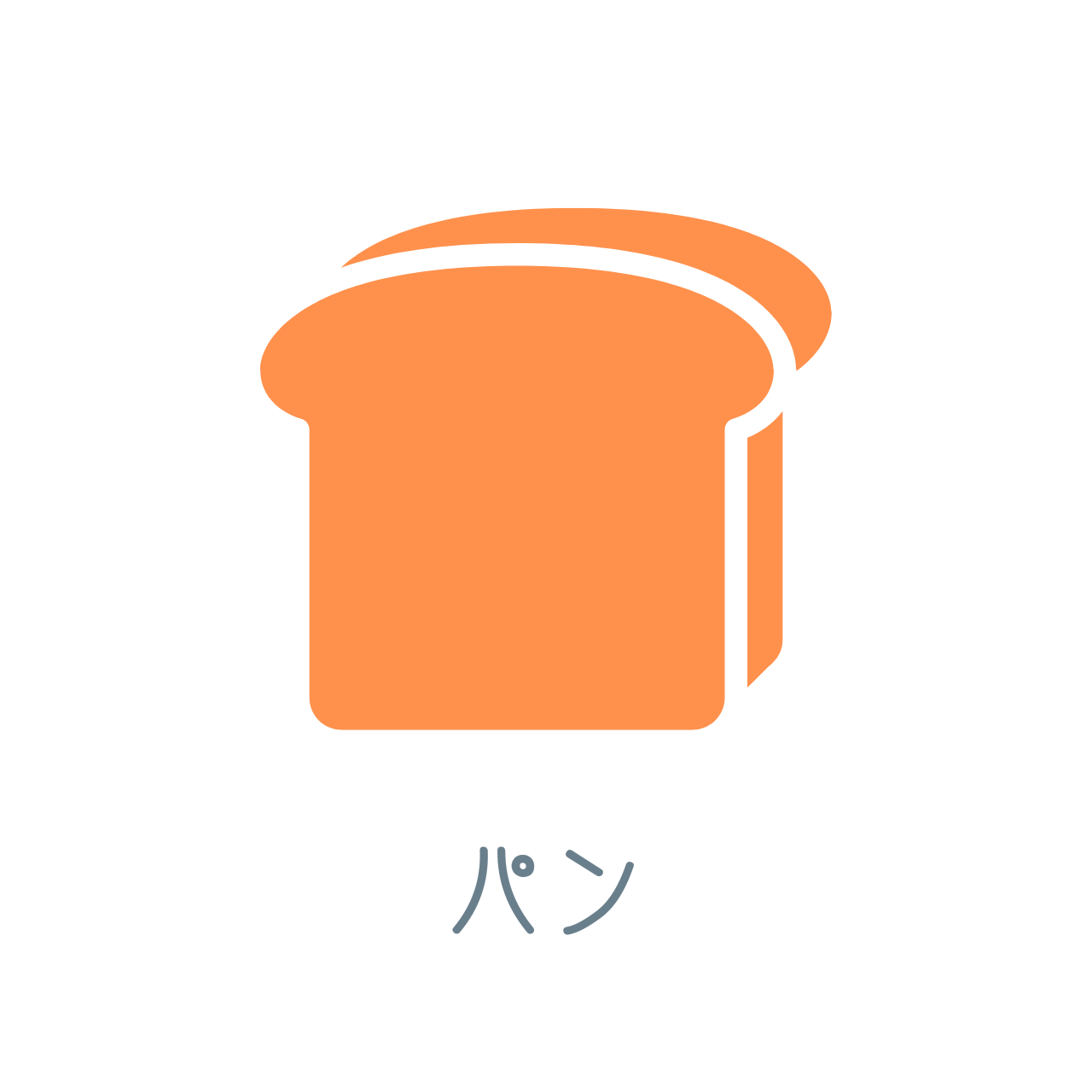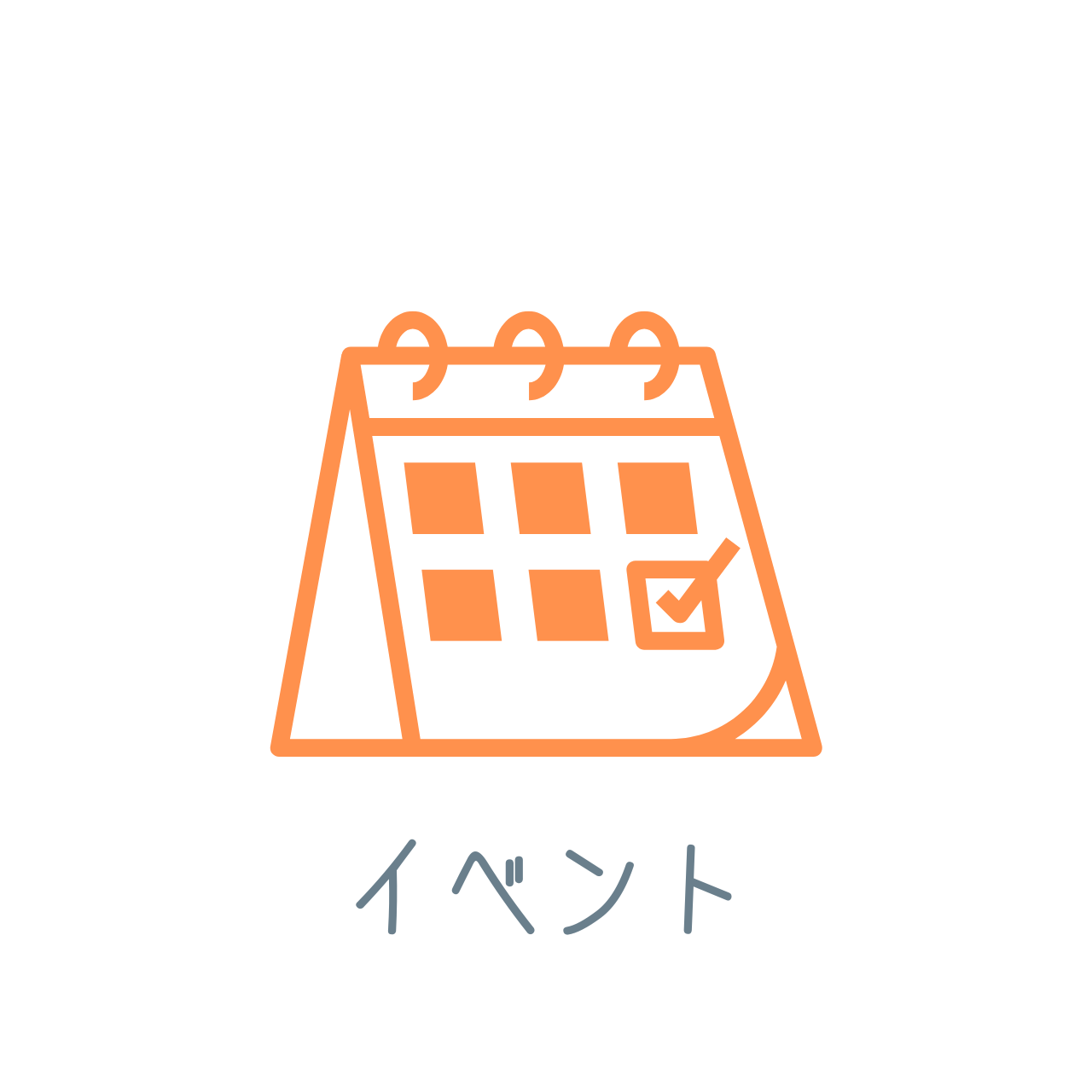アトピー性皮膚炎の新療法 県立医大など開発
和歌山県立医科大学は5日、アトピー性皮膚炎の炎症とかゆみを同時に抑制する新たな抗体療法を開発したと発表した。中等症から重症の皮膚炎を発症させたモデルマウスで病状の改善が確認され、今後、人間に対応する同様の作用の抗体が作製できれば、治療を短期間化し、患者の身体的、経済的負担の軽減につながることが期待される。医学部解剖学第二講座の森川吉博教授、小森忠祐准教授を中心とする研究チームによる成果。
【写真】研究成果を説明する森川教授㊨と小森准教授
アトピー性皮膚炎では、激しいかゆみに反応し、かく行動が皮膚の炎症を悪化させ、それがさらなるかゆみ、かきたくなる衝動を誘発する「かゆみ・掻破(そうは)サイクル」があり、治療にはこのサイクルの遮断が最も重要とされる。
現状、有効な治療薬として用いられるステロイドは、皮膚の炎症には効果を発揮するが、かゆみには直接的な抑制効果がなく、副作用や長期使用に伴う潜在的な毒性もあり、代替療法の開発が必要とされる。一方、かゆみの軽減に用いられる抗ヒスタミン剤や抗アレルギー薬は、重症患者の激しいかゆみにはほとんど効果がない。
今回、研究チームが注目したのは、アトピー性皮膚炎の発症に関連するサイトカイン(細胞間の情報をつなぎ、周囲の細胞に影響を与えるタンパク質)のうち、かゆみを引き起こす「インターロイキン(IL)-31」と、炎症に関連する「オンコスタチンM(OSM)」の二つ。
サイトカインは受容体と結合することで周囲の細胞に影響を及ぼすため、抗体で結合を阻害することにより、影響の発現を抑えられる。
研究では、OSMとIL-31に共通する受容体に対する抗体を投与したモデルマウスで、皮膚炎症の改善に加え、掻破行動が減少し、かゆみの抑制がみられ、アトピー性皮膚炎の主要な2症状を同時に抑える効果が確認された。
県立医大で記者会見した森川教授は、アトピー性皮膚炎について、3歳までの発症率が約30%で、寛解率は1歳6カ月までの発症では約70%だが、それ以降は約50%であり、多くの患者がいることを説明。激烈なかゆみで睡眠が妨げられるなどQOL(生活の質)を大きく損なうだけでなく、顔や首などに湿疹ができるため、社会生活に支障をきたすことも少なくない疾患であり、「単なる皮膚炎と考えてはいけない。社会的な問題を含んでいる」と述べた。
さらに、患者によって病態はさまざまで、既存の治療薬は効果に個人差が大きく、高額な投薬を長期に要する場合も少なくないことから、治療の選択肢が増えることが重要だと強調。「経済的な面も含めて患者負担が小さくなるよう、短期間、少量で効くことを目指している」と話し、今後の研究の進展に意欲を示した。
今回の研究成果は、アメリカの医学・生物学の専門誌「ファセブ・ジャーナル」のオンライン版で、昨年12月16日に掲載された。