

和歌山ラーメン誕生物語 ~第4話~ 「車庫前系スープのルーツ」
イチオシの記事
【連載コラム】和歌山ラーメン誕生物語
いまや全国的な知名度を持つ「和歌山ラーメン」。そのブームが生み出された経緯を知る筆者(S.Satoh.SD)が、後世に伝えるべく、ロカルわかやまに書き綴る第4話。
第3話までのあらすじ
時は1998年(平成10年)。同年1月に放送された「TVチャンピオン 日本一うまいラーメン選手権で、和歌山市の「井出商店」が日本一と紹介された。東京のマスコミからはノーマークだった和歌山のラーメン。それまで地元では誰も呼んでいなかった「和歌山ラーメン」との名称で紹介されることが多くなり、週末ともなると、マスコミで取り上げられた各店に行列が生じるように…。
第1話は こちら で読めます
第2話は こちら で読めます
第3話は こちら で読めます
和歌山中華そばのキーパーソン
編集部Horry(以下、H)「1998年秋に新横浜ラーメン博物館で『和歌山ラーメン』の企画展が準備され、その調査のために広報担当の武内伸さんが和歌山に来ていたんですよね」
私「あらすじの補足、ありがとう。武内さんは和歌山で『中華そば』の暖簾を見つけると片っ端から食べ、そしてお店の歴史を聞き出そうとした。でも、代替わりしていたりで、なかなか調査は進まなかった」
全国各地のラーメン処を調査した経験を持つ武内さんによると、ラーメンはあくまでも庶民の食文化のため、小難しい文献があるわけではない。また後継者がいない場合、店発祥のエピソードなどは時代の経過とともに消えてなくなるのが全国どこでも普通、というのが武内さんの見解だった。

私「情報誌制作を稼業としていた私は、初めて武内さんにお目にかかった際、自分が知っていることを披露した。そしたら武内さん、その話は○○のご主人が話していたことと一致しますねと、ノートをめくりながら1個ずつチェックしていくんよ」
H「裏付け捜査を行う刑事みたいですね」
私「歴史を解き明かそうとする際は必ず複数の証言を得ますって、ホンマに感心したわ」
そしてついに、当時私が勤めていた会社の社長と『丸髙アロチ本店』の2代目主人・高本英二さんの兄・高本在一さんが高校時代の同級生といったコネを使い、武内さんともども訪ねることに。
H「さすが和歌山、世間が狭い。で、いよいよ核心に迫れたわけですか」
私「いやいや、在一さんは『ワシよりも、母親に聞いた方が話は確かやで』となって、それまで一切の取材を受けなかった高本順子さんに話を聞けることになった。和歌山の中華そばのキーパーソンに会え、武内さんにめっちゃ感謝されたわ、うん」
H「“仕事やったわ感”を出さんといてください(笑)」
1940年(昭和15年)が発祥?
戦後、チンチン電車の車庫前に屋台集結

撮影者=山本潔さん
※「和歌山の中華そばとラーメン。」(発行/アガサス)より

以下は、武内さんが高本順子さん(高本光二氏の妻)から聞いた貴重な話である。私の当時の取材ノートに残っていたメモを編集して披露しよう。
●『丸髙』初代ご主人である高本光二氏は、1940年(昭和15年)頃から、和歌山市高松付近で中華そばの屋台を曳き始めた
●最初は鰹節とジャコを醤油で炊いたものを出汁にしてスープを作っていた。このスープを今の時代に出したら絶対においしくないだろうが、当時はみんな「おいしい、おいしい」と言って喜ばれた
●戦後になり食糧事情が良くなると、豚骨を使用するようになった。具はかまぼこでなく、光二氏のアイデアで松茸を使っていた。光二氏は製麺機を自分で作り、自分で打っていた。
●この味が大繁盛し、従業員を雇うほどの忙しさに。その人たちや、またその味を見真似で習得した人たちが独立。和歌山市内中心部を走っていた市電(チンチン電車)の停留所ごとに屋台を出し、当時は和歌山市の南部の繁華街だった車庫前停留所(現在は和歌山バス「高松北」バス停)付近には何軒もの屋台が連ねていた。
●1971年(昭和46年)にチンチン電車は廃止、屋台は和歌山市内各地で店舗になって営業を続けた。
私「以上が『車庫前系』と呼ばれるスープのルーツですわ」
H「車庫前系?」
私「武内さんは和歌山のお店を食べ走る(第3話参照)うちに、スープには2系統があることを突き止めた。醤油が主張する=車庫前系と、豚骨が主張する=井出系」
H「井出系とは、井出商店の味ですよね。確かに、丸髙、まるやま、丸木などと、井出商店、丸三、正善などとはスープに相違があります」
私「どこも醤油と豚骨は使っているので明確な線引きは難しいが、このことを言葉にしてカテゴライズした武内さんは、さすが博物館の人やわ」
H「昭和15年創業ということは、今年(2025年)は昭和100年にあたるから、和歌山の味が誕生して85年にもなるんですね」
私「それがやね、高本順子さんによると、高本光二さんが屋台を曳き始める前から屋台営業をしていた人物がいたらしい。井出商店の創始者である井出つや子さんに話を伺った際も、昭和初期に今の和歌山駅(当時は東和歌山駅)近くで屋台の中華そばを食べた記憶があったそうだ」
H「ということは、和歌山の中華そばの歴史は100年近くになるということですか」
私「武内さんの知識では、福岡県久留米市の『南京千両』が1937年(昭和12年)創業、京都市の『新福菜館』が1938年(昭和13年)創業で、両店が西日本最古参と言われているそうだ。和歌山の中華そばの歴史は、これらに匹敵するのかもしれない」
第5話へ つづく
【和歌山の一杯】
まるやま 小松原本店
1998年(平成10年)の「和歌山ラーメンブーム」時に営業していたお店を、2025年(令和7年)に訪れて食べたレポート。

和歌山の中華そばの歴史を語る上で、「車庫前」「チンチン電車」「電車道」というワードを目にすることは多い。チンチン電車が走っていた国道42号線(中央通り)に面して営業する店がここ『まるやま小松原本店』である。

1971年(昭和46年)まで走っていたチンチン電車。この写真は日赤医療センター前の陸橋の上から南を向いて撮影、チンチン電車が廃止される直前のもの。『まるやま小松原本店』は、この場所よりもっと南の右側。
個人談であるが中学の時、隣接する南川書店の前を休日のクラブ活動(練習試合など)の待ち合わせ場所にしていた(昭和の話)。店から漂うあの独特の香りは、昔も今も変わらず。前を通るたび、当時のことが頭をよぎる。
いやはや、何十年たってもこの味は健在。もう説明は要るまい。焼き飯、そして「おでん」が炊き込まれ、セットメニューとしての提供も。“大人の炭酸飲料”‟大人の水分“などもあり、すっかりオジサン・オバサンとなった昭和の少年・少女たちは、昼に夜に、ド定番の味に舌鼓を打ちながら癒やされる。

| 名称 | まるやま 小松原本店 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県和歌山市小松原6-1-14 |
| 電話番号 | 073-423-6071 |
| 営業時間 | 【平日】 11:00~15:00、17:00~翌1:30 【土日祝】 11:00~翌1:30 |
| 定休日 | 月曜 ※月曜が祝日の場合は営業し翌平日休み |
| 駐車場 | あり |
| @maruyama_komatsubarahonten |

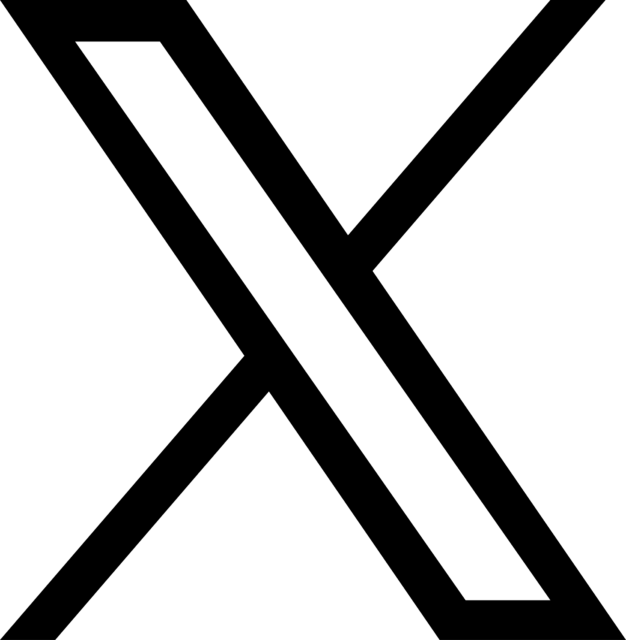

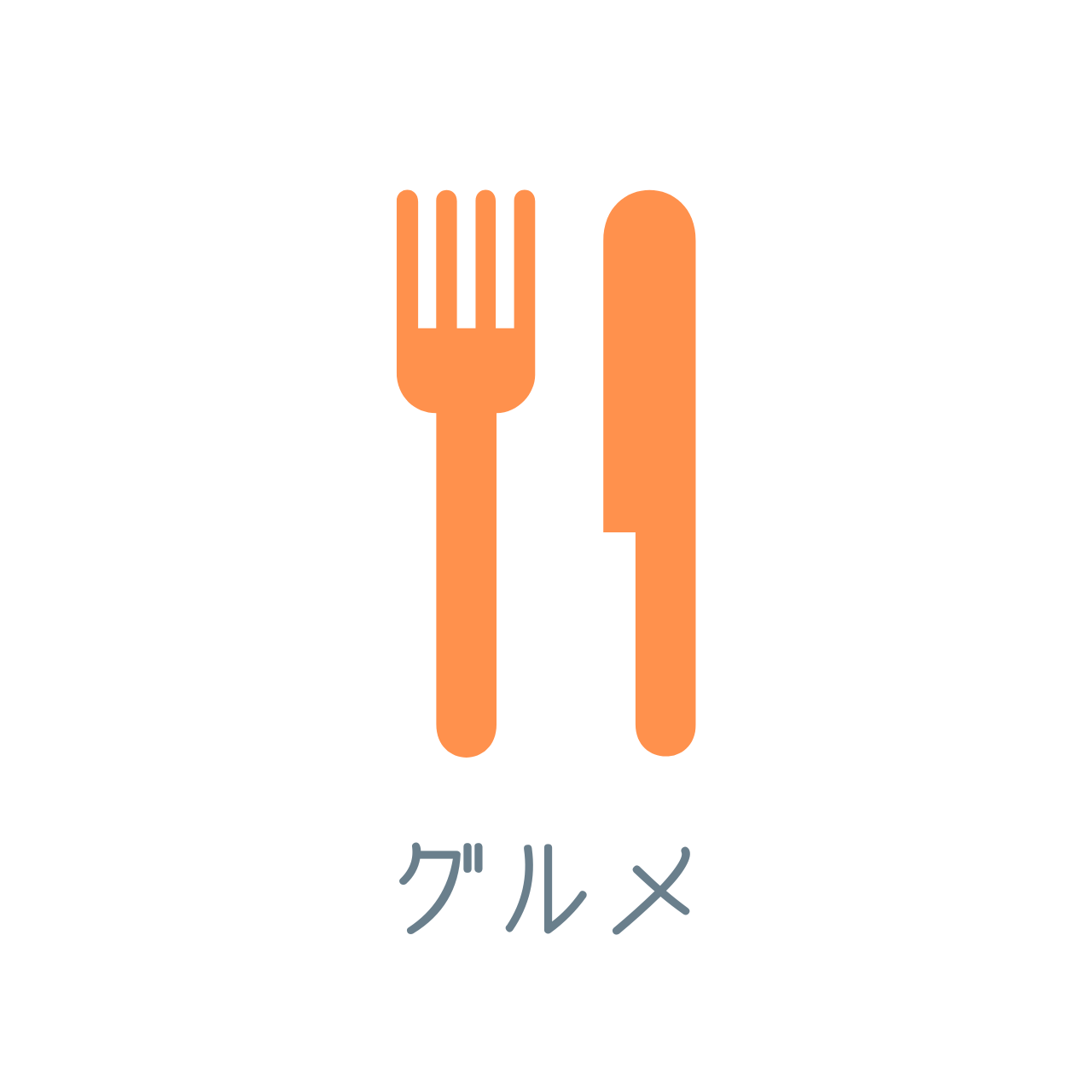

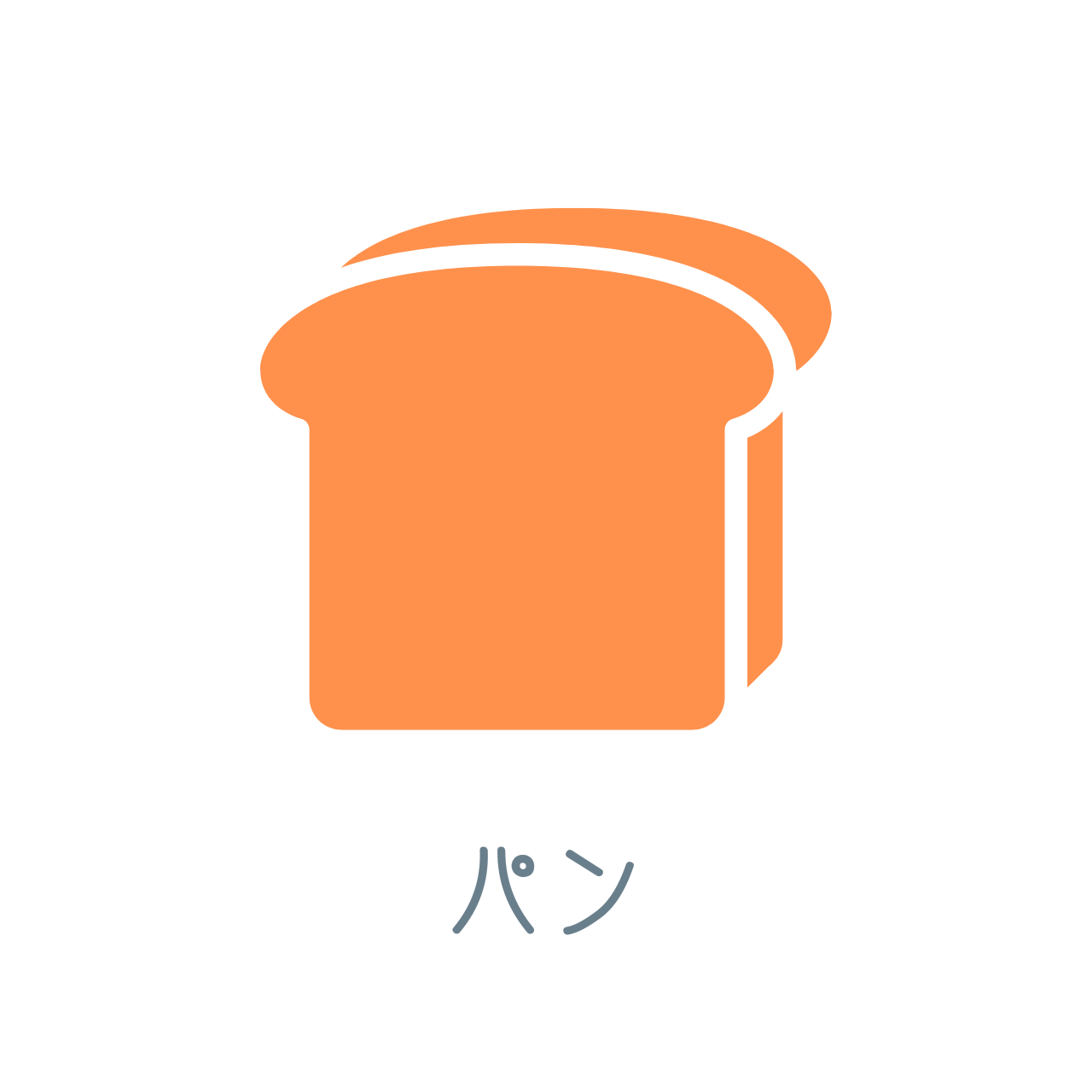




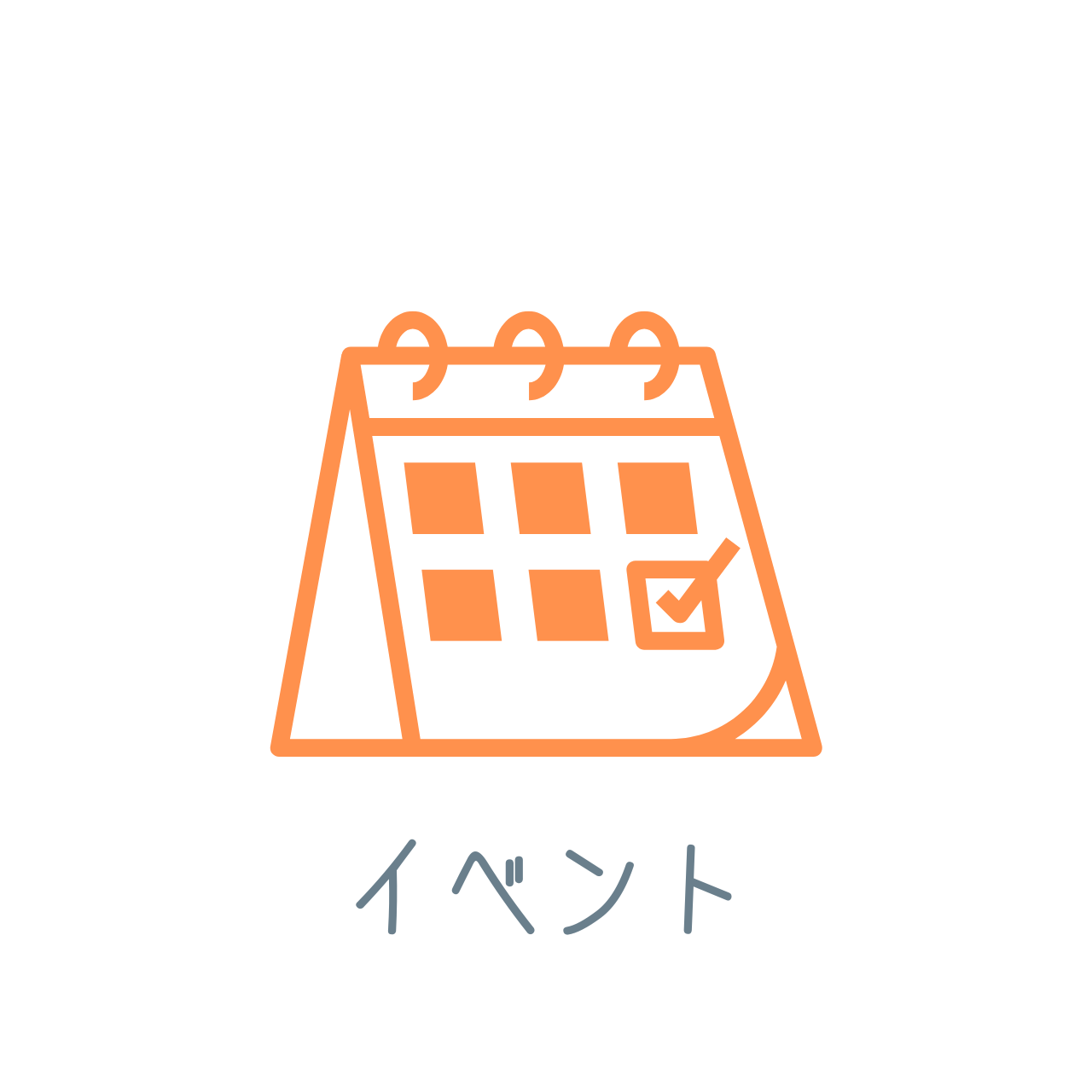











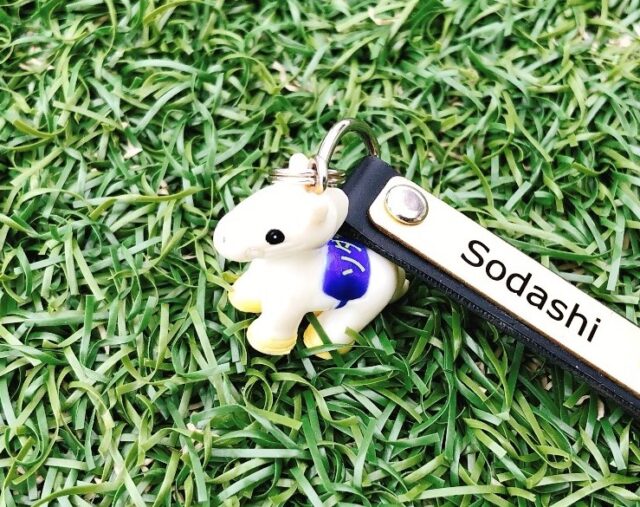








和歌山の麺歴史に詳しい、創業40年近くのエディター。嫌いな質問は、「おすすめのラーメン店を教えてください」。もし聞かれたら、「サッポロ一番みそラーメンが好きです」と肩透かし。